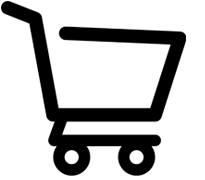失敗しないスタンドライトの選び方|おしゃれ部屋を間接照明に変える3つのポイント
スタンドライトは、置くだけで部屋の表情をがらりと変えてくれる照明です。北欧デザインのミニマルなものから、和モダン、インダストリアルまで、選択肢は驚くほど豊富。
リビングでも寝室でも書斎でも活躍します。でも「なんとなく」で選ぶと、思ったより暗かったり、部屋に馴染まなかったり。この記事では、失敗しないための3つのポイントと、購入前の最終チェックリストをまとめました。
【役割と効果】スタンドライトで「間接照明」の空間を演出する

スタンドライトの本当の価値は、ただ明るくすることではありません。壁や天井に光を反射させることで、眩しさを抑えながら空間に奥行きと陰影を生み出す。それが間接照明の醍醐味です。観葉植物の横に置けば葉の輪郭が浮かび上がり、アートの近くなら質感が際立つ。光の当て方ひとつで、部屋の印象は驚くほど変わります。
【配置のコツ】失敗しない!部屋別の配置ポイント
スタンドライトは、置く場所によって効果が大きく変わります。同じライトでも、リビングでは空間の広がりを、寝室ではリラックスを、書斎では集中しやすさを演出できます。ここでは部屋ごとに「どこに、どう置くか」の具体的なコツをご紹介します。
リビング:壁面を照らして奥行きを出す
ソファの脇や部屋の隅に置いて、壁面に向けて光を当ててみてください。天井と壁が柔らかく光り、空間全体がふわっと広がって見えます。テレビの背面に置けば、画面との明暗差が和らいで目も疲れにくくなります。
寝室:暖色光でリラックスできる空間に
寝室には、2700〜3000Kの電球色がおすすめ。調光機能があれば、眠る前に少しずつ光を落としていけます。ベッドサイドに置くなら、眩しさを感じない高さと向き、そして寝転んだ状態でスイッチに手が届くかどうかもチェックポイントです。
書斎:手元と背景の明暗差をコントロール
デスク作業では手元の明るさが大切ですが、背景が真っ暗だと画面とのコントラストが強すぎて目が疲れます。手元用の照明とは別に、背景にほんのり間接光を入れると集中しやすくなります。可動式アームや配光を調整できるタイプなら、作業内容に合わせて使い分けられて便利です。
【光の質】おしゃれに見せるための光の使い方
同じスタンドライトでも、光の向き、色温度、素材によって印象はまったく変わります。「どこを照らすか」「どんな色の光か」「どう反射させるか」——この3つを意識するだけで、空間が見違えるほど上質になります。
光の方向
光をどこに向けるかで、印象は大きく変わります。壁、天井、カーテンなど「面」を照らすと上質に見えます。逆に、光源そのものが直接目に入ると眩しく感じるので、発光面は視界から隠すのがコツです。
色温度
くつろぎたいときは電球色、作業には昼白色が基本です。シーンによって切り替えたいなら調色機能付きを選ぶと良いでしょう。照明は「明るさ」よりも「光の質」が印象を左右します。陰影をどうコントロールするかが、空間を上質に見せる鍵です。
反射・素材

シェードの素材も重要です。布や和紙は光を柔らかく拡散し、ガラスや金属はシャープな反射を生みます。床や壁、家具の色や質感と合わせて選ぶと、部屋全体に統一感が生まれます。
【購入前チェック】デザイン・機能から決める最終チェックポイント
購入前に、この5つを確認しておくと失敗がぐっと減ります。
□ 高さと照射範囲は部屋の広さ・天井高に合っているか
□ 調光・調色機能は必要か(時間帯や用途で使い分けるか)
□ スイッチ位置・コード長は使いやすいか(足元・手元・リモコン)
□ 素材・色が内装と調和しているか(床・壁・家具との相性)
□ 光源交換・メンテナンス性や保証内容は十分か
まとめ:あなたに最適なスタンドライトを見つける
スタンドライトは、暮らしを「照らす」だけでなく「整える」存在です。役割・配置・光の質の3つを押さえれば、失敗はほぼ防げます。あなたの空間にぴったりの一台を見つけてください。
スタンドライト特集を見る