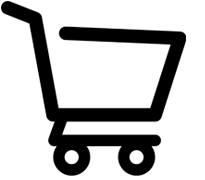ブラケットライトとウォールライトの違いとは?呼び方と選び方を照明士が解説
壁に取り付けて空間を演出する照明を探していて、こんな疑問を持ったことはありませんか?
「ブラケットライトとウォールライトって何が違うの?」、「どっちで検索すればいいんだろう?」
実は、どちらも壁面照明を指す言葉で、機能的な違いはほとんどありません。ただ、使われる場面や文脈によって微妙なニュアンスの違いがあります。本記事では、照明士の視点からその使い分けと、空間に合った選び方をわかりやすく解説します。
ブラケットライトとウォールライトの違い
結論から言えば、機能や構造に明確な違いはありません。どちらも壁に取り付けて空間を照らす照明であり、「呼び方が違うだけ」と考えて問題ありません。
ただし、使われる場面には傾向があります。
国内では「ブラケットライト」が主流で、建築・インテリア業界では「壁付照明」「壁面灯」と同義で使われています。一方、「ウォールライト(ウォールランプ)」は英語圏由来の呼び方で、輸入照明やデザイン照明の分野でよく見かける表現です。
つまり、どちらも同じものを指していますが、文脈や業界によって使い分けられているということです。次のセクションでは、その使い分けの背景をもう少し詳しく見ていきます。
言葉の使い分けと由来

では、なぜ同じ照明に複数の呼び方があるのでしょうか?それは言葉の由来と、使われてきた文脈の違いにあります。
【言葉の由来】
・ブラケット(bracket):金具・支持具を意味する英語。「壁に固定して取り付ける構造」そのものを指す言葉として定着しました。
・ウォールライト(wall light):英語で「壁面照明」の総称。"light on the wall"の略で、デザイン的・感覚的な表現として用いられます。
【使われる文脈の違い】
国内では、「ブラケットライト」は建築業者や電気工事の現場で使われる施工用語・機能名称としての側面が強いです。配線工事や取り付け方法を調べる際には、この言葉で検索すると正確な情報が見つかります。
一方、「ウォールライト」「ウォールランプ」は、雑誌やショールーム、インテリアコーディネートの文脈で多用されます。ユーザーの「おしゃれにしたい」という感覚的な検索意図に強く結びついており、国内外のデザイン実例を探す際に有効です。
【実践的な使い分けのコツ】
・仕様や工事内容を調べたい → 「ブラケットライト」で検索
・デザインやイメージを探したい → 「ウォールライト」「ウォールランプ」で検索
呼び方の違いを理解しておくと、情報収集がスムーズになります。
設置シーン別の選び方

玄関・廊下:上下配光タイプで柔らかい陰影を演出します。高さは床から約1.6〜1.8mが目安です。人の目線より少し上に光を配置することで、まぶしさを感じにくく、心地よい明るさを保てます。
【よくある失敗】
玄関に設置したブラケットライトが床から1.4mの位置にあり、立ったときに光源が目線の高さに来てしまうケース。帰宅のたびに眩しさを感じ、せっかくの演出照明がストレスの原因になってしまいます。
【プロの配置】
床から1.6〜1.8mの高さに設置することで、人の目線より少し上に光を配置でき、まぶしさを感じにくく心地よい明るさを保てます。
【専門解説:グレア防止の理由】
玄関や廊下は人が立ち止まらずに移動する動線です。シャンデリアと異なり、光源が目線の高さにあるとグレア(眩しさ)を感じやすく、視界の妨げになります。床から1.6〜1.8mの高さは、「立っている人の視線から光源を外す」ためのプロの定石であり、導線確保に最も適しています。
寝室:読書灯にはアーム付きタイプ、間接照明には拡散タイプが最適です。ヘッドボードの上や壁面のサイドに設置することで、落ち着きのある照明環境をつくれます。
【専門解説:寝室における設置のコツ】
アーム付きタイプを選ぶ際は、光源が寝ている人の目線に入らないように、シェードの向きを調整できるモデルを選びましょう。また、就寝前に使用する間接照明として使う場合は、光源が完全に隠れる「間接配光タイプ」を選ぶと、光だまりが生まれ、深いリラックス効果が得られます。
リビング:シャンデリアやスタンドライトと組み合わせることで空間に奥行きが生まれます。壁際の照明は、天井や床に柔らかな陰影をつくる“補助光”としても有効です。
【専門解説:リビングでの役割】
リビングでは、ブラケットライトを主照明(シーリングライトなど)の補助的な役割として使うことで、空間に立体感と奥行きが生まれます。アートやオブジェを照らすアッパーライトとして活用したり、壁面の凹凸を際立たせることで、単調になりがちな広い空間にアクセントを加えることができます。
素材と光の印象の違い

素材によって光の広がり方が大きく異なります。スタイルとの具体的な組み合わせを意識しましょう。
【素材とスタイルの組み合わせ例】
・クリアガラス × 真鍮フレーム = クラシック・エレガント
→ 玄関やダイニングなど、華やかさを演出したい空間に
・乳白ガラス × アイアン = モダン・シンプル
→ 寝室やリビングなど、落ち着きを重視したい空間に
・布シェード × 木製フレーム = ナチュラル・北欧
→ 寝室や書斎など、温かみのある空間に
素材の組み合わせを意識するだけで、空間との調和が格段に高まります。
ガラス製(拡散・透明感)
柔らかく拡散する光で優しい雰囲気をつくります。リビングや寝室など、くつろぎ空間に最適です。
乳白ガラス: 光を均一に広げ、空間全体に穏やかな明るさを提供します。
クリアガラス: 周囲の壁に光の粒(影や模様)を散らし、煌めきとアクセントを加えます。
真鍮・アイアン製(陰影・重厚感)
陰影が際立ち、クラシックやヴィンテージ調のインテリアに最適です。時間の経過とともに風合いが深まり、重厚感のある印象を与えます。
乳白ガラス:
真鍮はアンティークやヴィンテージといった温かみのあるスタイルに、アイアンはインダストリアルやモダンといったシャープなスタイルに好んで用いられます。シェードの有無も光の印象を大きく左右します。
布・木製(ナチュラル・温かみ)
ナチュラルで温かみのある空間づくりに向きます。特に北欧スタイルやナチュラルモダンな部屋では人気の素材です。
【光の質の特徴】
布シェードは光を優しく吸収し、空間全体を穏やかなトーンに包み込みます。この光の質は、ホテルライクな落ち着きのある印象を与えたい場合に非常に有効です。
まとめ:呼び方の違いよりも空間に合う照明選びを

ブラケットライトもウォールライトも、壁を照らす照明という点では同じ存在です。呼び方にこだわるよりも、次の3つを意識して選びましょう
1. 設置場所:玄関なら上下配光、寝室ならアーム付きなど、用途に合った配光を選ぶ
2. 高さ:床から1.6〜1.8mを基準に、グレア(眩しさ)を防ぐ位置に設置する
3. 素材:ガラスは透明感、金属は陰影、布・木は温かみ——空間のスタイルに合わせて選ぶ
光の位置や素材の選び方を少し意識するだけで、部屋全体の雰囲気は驚くほど変わります。あなたの空間に合った一灯を見つけてください。